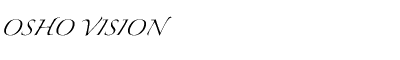OSHO 講話

光明を宣言しなさい
I want you to
Decleare Your Enlightment
“Om Mani Padme Hum”より抜粋
光明を宣言しなさい ――あなたの平凡さがいかにして光明の輝きへと花開くのか をOSHOは説く――
愛するマスター
私たちはみんな光明を得ているとあなたがおっしゃっていると聞きました。もしそうだとしたら、なぜ私は何かが起こるのを待っているのでしょうか。古い習慣でしょう
か?
ヴィート・ヴィギャナム、たんに聞いただけではなくて、ほんとうに理解しなければいけない。確かにあなたは私が「私たちはみんな光明を得ている」と言うのを聞いたが、それを信頼しなかった――あなたは自分だけを除外した。「たぶんみんなはそうなのかもしれないが、まさかこの僕が?」あなたにはとても受け容れられなかったので、こんな質問をした。
この質問はあなたの奥深くに混乱があることを示している。あなたは「もしそうだとしたら……」と言っているが、私はあなた方の光明がなんらかの確率のようなものだと言ったのではない――もしかしたら光明を得ているかもしれないし、もしかしたら得ていないのかもしれない。そこに「もし」や「だが」はなかった。それは単純な言明だった。もう一度、繰り返そう――
あなたは光明を得ているし、そうであるしかない。
だが、あなたの困難は理解できる。あなたはおまえは無知だと言われてそれを受け容れてきた。あなたはおまえは無価値だと言われてそれを受け容れてきた。あなたはおまえは美しくないと言われてそれを受け容れてきた。「もし」や「だが」を言うことなく、質問さえせずに自分がどれだけのことを受け容れてきたのかを見てみるといい。
ほんの小さな子どもの頃から、あなたは正しい見方を与えられてこなかった。あなたはいつもあっちへこっちへと押したり引っぱったりされてきた――「これになりなさい、あれになりなさい」と。誰ひとり、もしも存在がゴータマ・ブッダだけを望んだのなら、存在はゴータマ・ブッダをフォードの工場でフォードの自動車が生産されるように、流れ作業で、なにもかもがまったく同じように、きわめて効率よく製造することもできたのだということを考えた者はいなかった。流れ作業の工程からは、一日二十四時間、毎分一台の自動車がつくりだされてくる。
だが存在は誰もが他のみんなと同じようになる状況をよいものだとは思わない。ゴータマ・ブッダの光明は彼の光明であってしかるべきだ。あなたの光明はあなたの光明であってしかるべきだ。
比較から問題が生じてくる。あなたはこのように考えはじめた――「もし僕が光明を得ているのなら、どうして僕はゴータマ・ブッダやイエス・キリストやボーディダルマのようではないのだろう。僕はヴィート・ヴィギャナムであるにすぎない。誰も僕を尊敬してくれない。僕が歩き回っても、僕のことに気づいてくれる人さえいない。こんなものが光明だろうか? きっとこれから達成しなければいけないんだ。きっとそれはまだ起こっていないのだから、これから起こらなければいけないんだ」
その考えがこれほどの一貫性を持って、じつに何千年にも渡って、世の中に広められてきた――光明は達成されるものなのだという。私はあなた方に言いたい、光明は達成ではない、それはあなたのまさに本性だ。もしあなたがそれを見逃しているのだとしたら、理由はあなたがそれを達成していないからではない、理由はあなたが自分自身を除くほかのあらゆる場所でそれを探し回っているからだ。あらゆる寺院に行き、あらゆる聖典を読み、マスターの振りをしているありとあらゆる愚かな人たちを訪ねて回っている。
自分は光明を得ているのだといままさにこの瞬間に宣言してほしい。みんながあなたを崇拝するかどうかは問題ではないし、そんな必要もない。どうしてみんながあなたを崇拝しなければいけないのか。あなたは光明に無用な条件を課している。
これはあなただけの問題ではなく、多くの人にとっても問題だった。仏教徒はマハヴィーラが光明を得ていることを認めることができない。彼は裸で暮らしているがゴータマ・ブッダは裸で暮らしていないからだ。ゴータマ・ブッダには美しい髪の毛があったがマハヴィーラは自分の髪を引き抜いた。このふたりの人がどちらも光明を得ているはずがない。
私たちは、よく考えもせずに、光明を得た人はみんな同じはずだという考えを受け容れてしまっている。これはまったくのナンセンスだ。存在では、多様性がその美しさだ。
私もまた誰もが自分なりのやり方で光明を得て自分なりのやり方でその光明を表現してほしいと思う。そうでなかったら世の中全体が退屈きわまりないものになってしまう。考えてみるといい――イエスが弟子たちに言ったように――「誰もが自分の十字架を運ばなければならない」。まわりを見まわして、誰もが自分の十字架を運んでいる光景を想像してみなさい……彼らを磔にする者さえいない。その者たちも十字架を運んでいるからだ。なにもかもがばかげたお祭り騒ぎになってしまう。
存在は二度と同じ人間をつくりださない。類似性はこの美しい宇宙のルールではなく、独自性がそのルールなのだ。そして独自性を受け容れる瞬間に、あなたはあるがままの他人へのこの上もない敬意をも受け容れる。
もっと別の言い方をしてみよう。自分自身を光明を得た存在として敬うようになった瞬間から、あなたは誰しもをあるがままで光明を得た存在として敬うほかはなくなってしまう。誰もが一定のカテゴリーに当てはまる必要はない。光明はカテゴリーではないからいつも同じ食べ物を食べていなければならないわけではない。もしもそのような一定のルールがあったら、私はスパゲッティなんか食べるよりも光明を放棄していただろう。どんな聖典もスパゲッティは光明を得た人のなくてはならない特徴だと言っていないのはけっこうなことだ。
私の言うことを理解したなら、私が言っていることを――あなたはその平凡なままで完璧に正しいのだと私は言っている。なにひとつあなたに付け加えなければならないものはない。そしてもしこの平凡さにくつろぐことができたら、このまさに平凡さが、あなたのくつろぎゆえに、輝かしいものになって、花開きはじめるだろう。あなたの受容性が、あなたの自分に対する敬意が滋養になって、あなたの存在に春をもたらし、花々はその花びらを開きはじめるだろう。
だがあなたはけっして自分の我が家でくつろがない。あなたは他人の家をのぞき込んでいる。誰かはゴータマ・ブッダの家を、誰かは老子の家を、誰かはイエス・キリストの家を、誰かはモーゼの家を……これはじつに奇妙な状況であり、あなたはわき道にそれて、誰もがほかのどこかに、いてほしくない場所にいて、存在がいてほしいと思う場所にはいない。
私は即座にして究極の平凡さを教える。それは最も美しい体験だ。なぜなら、いまや欲望はなく、緊張はなく、探求はなく、問いかけはなく、行く場所はないからだ。あなたはすでに自分がいたかった場所にいる。
そしてあなたは「もしそうだとしたら、なぜ私はなにかが起こるのを待っているのでしょうか」と尋ねている。さて、私はこれに答えるべきだろうか。おそらくこれはあなたの独自の光明ではないだろうか。ほんとうは光明を得ているのに、なおもなにかが起こるのを求めているということは。ちょっとクレージーだが、それがあなたの光明を壊してしまうわけではない。それに何人かクレージーな人びとも必要だ。彼らは存在に塩味をもたらす。クレージーな人たちがいない存在からはなにかとても興味深いものが失われてしまう。
だがあなたはそれさえも受け容れることができない。あなたはなおも続けてこう尋ねる、「古い習慣でしょうか?」。たんに自分自身を慰めようとして、あなたははほんとうは光明を得ているのだが、たんに古い習慣ゆえにあっちこっちを探し回っている。だがあっちこっちを探し回るほどに、あなたはますます古い習慣を肥やすことになる。古い習慣を練習している。
食べ物を静かに喜びに満ちて食べ、たたえられるいっぱいの至福とともに眠り、大工として、靴屋として、画家として、詩人として、ダンサーとして平凡な人生を送り、理想を抱くことなくありのままの自分にリラックスする……という姿を見るのは非常に難しい。だが人間は理想がなくても死にはしないし、理想がなくても奴隷にされることはない。なるべき理想像がなかったとしても彼を非難することはできないし、彼に罪悪感を感じさせることはできない。それに一生をかけてなろうとしても理想のとおりになった人はひとりもいない。
キリストになったキリスト教徒を見たことがあるだろうか。人類のほとんど半分がキリスト教徒で、二千年にも渡ってこれらの人びとはキリストになるという理想をかなえようと懸命の努力をしてきた。なぜ彼らは失敗しつづけるのか。それはキリスト教徒だけではない――ジャイナ教徒も、仏教徒も、イスラム教徒も、誰も成功してはいない。
理由はあまりにも基本的なので逆らうことはできない。
自分自身であるか、無駄骨折りをするかどちらかだ。
選択肢はこのふたつしかない。
ゴータマ・ブッダの独自性を愛するのはいいが、けっして彼のまねをしてはいけない。彼自身、誰のまねもしなかったので、そのために彼は光明を得た。単純な事実が認識されてこなかったのは奇妙なことだ。マハヴィーラは誰のまねもしなかったのでそのために光明を得た。誰かのまねをして光明を得た人がいたら見せてほしいものだ。
あるとても美しい人、カビールのことを思い出した。インドでは、ヒンドゥー教徒はガンジス河は聖なる河であり、ガンジス河の近くで死んだら間違いなく極楽に入ることができると信じている。あなたがどんな犯罪にかかわっていたのであれ、どんな罪を犯したのであれ、どんな不道徳なことをしたのであれ問題ではない。あらゆることがガンジス河によって洗い清められる。
もちろん、すべてのヒンドゥー教徒がガンジス河のそばで暮らすわけにはいかない。人が多くなりすぎてしまうからだ。そこに住んでいる人たちは幸運だ。そこに住むことができない人たちは少なくとも年をとったら、死が近づいてきたらそこに行って住む。ヴァラナシのような都市では、あなたもそれを見たら驚くことだろう――なぜこんなにたくさんの年老いた人びとが、年老いた女性がいるのだろうか、と。これに関してはどんな都市もかなわない。これらの人びとはみんなそこに死にに来て、自分の
死が訪れるのを待っている。それはいつやって来るかもしれない。
ときに近くの村でこういうことが起こる……ヴァラナシは物価が高いので、死ぬためにそこに暮らすことができるのは金持ちの人たちだけだ。貧しい人たちは近くの村に住む。だから彼らがその村で死ぬこともよくあるが、ただちに友人や親戚たちがその死骸をガンジス河に運んでいく。たいしたことではない、ほんの数分か、半時間か、一時間もあれば……神もそんなに無慈悲にはなれない。神はこれらの人たちの罪も許さなければならない。
カビールはその生涯をヴァラナシ、ヒンドゥー教徒にとって最も神聖な都市で過ごした。ガンジス河のちょうど向こう岸に、マガハールと呼ばれる小さな村がある。ヴァラナシで死んだ人は楽園に行きマガハールで死んだ人はロバになるという考えがどうやって広まったのか私は知らない。マガハールはガンジス河の向こう岸にある。
死期が近づいたことを感じたカビールは、友人たちに言った、「マガハールに連れていってくれ」
彼らは言った、「気は確かかね。マガハールで死にたがる人なんかいないよ。あそこで暮らしている人たちは年中恐れているんだ――死ぬ前にここから逃げ出さなければならない、と。君は一生をヴァラナシで過ごしていまや、いよいよその時が来たというのに、マガハールへ行きたいと言うのかい。マガハールで死んだ人がロバになるというのは君もよく聞いているだろう」
カビールは言った、「私の言うことを聞いてくれないのなら、マガハールまで歩いていかなければならない。だがガンジス河であろうと神であろうと、私にはこれっぽっちの負い目もない。もし私が光明を得ているのなら、私はヴァラナシでも光明を得ているし、マガハールでも光明を得ている。私が先例になろうではないか。なぜなら、気の毒なマガハールの人たちは何百年にも渡って非難されてきたからだ。私はマガハールで死のう。というのも、私が死んだ後ではマガハールで死んだ人はロバになるとは
言いにくくなるからだ。少なくともカビールにはそれを言うことができない」
カビールはマガハールで死んだ。彼はそれを変えた。いまでは誰もマガハールで死んだ人はロバになるとは言わない。むしろ反対に、カビールを愛する多くの人びとがマガハールに住んでいる。マガハールはカビールの信奉者たちの聖地になった。
もうひとりの神秘家、女性神秘家のミーラが巡礼のためにヴァラナシを訪れた。ヴァラナシにはヒンドゥー教の学者たち、世に賢いと言われる人たち、聖者たちの最高の評議会があった。ここで問題だったのは、この人たちの多くがカビールを自分たちの定例の会議に招きたいと思っていたのだが、カビールが織工だったことだ。それだけではなく、彼がヒンドゥー教徒であるのかイスラム教徒であるのかもはっきりしなかった。彼の名前はイスラム教から来ていた――カビールとはアラビア語ではアッラー、
神の別の名前だ。彼はガンジス河の岸辺でヒンドゥー教の僧侶ラーマナンダに見いだされた――幼い子どものときに、両親に置き去りにされた。この話はとても美しい……。
それはまだ暗い、ヒンドゥー教徒たちが太陽への礼拝の前に沐浴をする、早朝のことだった。ラーマナンダが階段を降りていくと、幼い子どもが彼のローブをつかんだ。驚いて――誰だろう、と――彼は見た。まだ四歳も越えていない、幼い子どもが、階段に坐っていた。この子はどうしたのだろう? まわりには誰もいなかった。この子どもはここに両親に置き去りにされたのだ。
ラーマナンダは勇気のある人だった。彼はその子どもを引き取った。弟子たちはみんな彼にこう言ったのだが。「あなたは無用な危険を冒すことになりますよ。あなたはヒンドゥー教徒たちによって、あなたを崇拝するのと同じ人たちによって糾弾されるでしょう。あなたがそんなことをすべきではありません。それだけでなく、その子の手にはアラビア文字で『カビール』と、名前が書いてあるではありませんか。これは彼がイスラム教徒であることの確かな証しです。それにヒンドゥー教の僧侶が子ども
を持つべきではありません、世を捨てているのですから」
だがラーマナンダは言った。「私は崇拝者、信奉者たちを得るためになにかをしたことはない。彼らが来たのだとしたら、彼らは自分から来たのだ。私は他人になにかをしろと命令したことがないのだから、誰も私になにかをしろと命令することはできない」。こうしてカビールはラーマナンダによって育てられた。ラーマナンダゆえに人びとは彼をヒンドゥー教徒であるに違いないと考え、その名前ゆえに人びとは彼をイスラム教徒であるに違いないと考えた。
そしていま、彼は当時の最も賢い人として知られるようになったので、何人かが彼をヒンドゥー教の神聖な会議に招きたいと考えた。彼は織工だった。多くの人びとが反対した。だが彼らは評議会を分裂させたくなかったので、最後には彼を招待することで同意に達した。
だが彼らがカビールを招きに行くと彼は条件を課した。「ミーラが私のところに泊まっていますから、彼女も招いてください。私はどうでもいいんです。私の代わりにミーラを招いてください」
だがこれはさらに難しかった。彼女は女性だった。ヒンドゥー教の賢者の評議会に女性が招かれたことは一度もなかった。女性は清らかであると認められない。基本的に女性は不浄であり厳しい修行をして男性として生まれ変わらないかぎり、女性は楽園に入ることができない。女性のままで楽園に入ることはできない。まず男性にならなければいけない。カビールはいまやさらに難しい条件を課していた。
彼らは彼に言った。「あなたを招待することでさえ非常に難しかったのに、さらに難しい条件をつけるのですか」
彼は言った。「私は自分の言ったことを変えるつもりはない。ミーラに敬意を払わないのならあなた方はなにもわかっていないということになるし、私は無知な人たちと付き合いたくはない」
カビールの信奉者たちは彼に言った。「これはまたとない機会です。いまだかつてひ
とりとして織工が」――織工はヒンドゥー教の最下層のクラスだ――「バラモンたち
から賢いと認められたことはないんですよ。この機会を逃してはいけません」
ところがカビールは言った。「私が賢いか賢くないかは自分で決めることだ。私は誰かが認めるか認めないかに依存しない。私がこの条件をつけたのは、ヒンドゥー教徒は何百年にも渡って女性にじつに醜い仕打ちをしてきたが、いまやそれを変えるべき時が来たと思ったからだ」
カビールの主張によって、ミーラはヒンドゥー教の賢者の評議会に参加した唯一の――初めての――女性となった。そこにはひとりのイスラム教徒がいたし、ひとりの女性もいた。ヒンドゥー教徒の清浄さや優越性の概念は粉みじんに打ち砕かれた。
カビールは生涯を織工として過ごした。国王ですら彼の弟子になり、彼にこう頼んだものだ。「私たちはあなたがそのお年になっても機織りの仕事を続け、自分で織った布を市場に売りに行かれることを恥ずかしく思っています。あなたがご入用なものはすべて用立てましょう。そんなことをする必要はないのです」
カビールは言った。「それは大切なことではありません。私は未来の人たちに織工でも光明を得ることができるし、光明を得ても機織りを続けることができることを思い出してもらいたいのです。織工というありふれた職業は光明の邪魔にはなりません。むしろ反対に、その機織りが彼の祈りになるのです。なんであれ彼のすることは祈りになります。なんであれ彼のすることは瞑想になります。なんであれ彼のすることは存在への感謝の表現になります。彼はたんにこの世の重荷になることはなく、なんで
あれ自分のできることをするのです。
「私は彫刻家にはなれないし、偉大な画家にもなれませんが、誰も私の織るように布を織ることはできないとなら言うことができます。私は一息ごとに祈りと感謝を込めて折るのです。私の折る布はたんに市場で売るためにではなく、神に仕えるため、私にできる最良のやり方で存在に仕えるために織られるのです」ヒンドゥー教で神を意味する言葉はラームだ。彼は自分の店に来たすべての客を同じ「ラーム」という名前で呼んだ。彼は言ったものだ。「ラーム、私はあなたのために布を織りました。これはただの布ではありません、大事にしてください。その糸の一本一本が私の感謝と愛と慈しみと祈りに震えているのです。これを大切にしてください」
ときにこういうことがあった……遅くまで、もう市場が閉まろうというのに、彼は待っていた。人びとが尋ねた。「誰を待っているんですか? もう市場は閉まりますよ」
すると彼はこう言った。「私はラームを待っているんです。まだおいでになっていませんが、私は彼のためにこの布を織ったんです」ある人が彼に注文し、その人はその日はひまがなかったか、あるいは次に市場が立つ日に来ようと思ったのかもしれない。だがカビールはそこで待ちつづけていた。
人びとは彼に知らせた。「なにをしているんですか。こんなに遅くまで、カビールひとりだけが、市場に坐ってあなたを待っているんですよ。『ラームが忘れてしまうなどということは、あるいはラームが自分の言葉を裏切るなどということは考えられない。たとえ七日待つことになっても待たねばならない』と言って」というのもインドでは、田舎では、市は週に一度、月に四日しか開かれないからだ。「七日でも待つことにしよう。なにか問題が起きたのかもしれないし、病気になったのかもしれない。だがこの場所から動くわけにはいかない。もし彼が来て、私がここにいないのを見つ
けたら、じつに残念なことになってしまう」
さて、ゴータマ・ブッダはまったく異なった生き方をした。ミーラはまったく異なった生き方をした。ミーラは国中を踊ってまわり、最後にはクリシュナの大神殿が建つ、マトゥラを訪れた。神殿の僧侶は狂信的な独身主義者だった。私はバッタチャリヤ教授によく言ったものだ。「あなたはあの狂信者の生まれ変わりです。この狂信を捨てないかぎり、リラックスすることはできないし、輪廻から解放されることはできませんよ。何度も何度も生まれ変わらねばならないんです」
クリシュナの神殿に女性が入ることは許されなかった。女性は外側から礼拝することしかできなかった。その僧侶は三十年間も女性を見たことがなかった――外出はしなかったし、女性が神殿の内部に立ち入ることはできなかったからだ。ミーラのことを聞いたとき、彼は心配した。彼女がクリシュナの大神殿に来ることは間違いなかったからだ。彼は入り口にふたりの門番を立てた。「あの女が踊りながらここにやって来たら止めるんだ」と。
だがミーラが踊りながらやって来ると、門番たちは完全に自分たちの目的を、なぜそこに立っているのかを忘れてしまった。そのダンスはとても美しくミーラもとても美しかったので、まばゆいばかりだったので、彼女は誰にも気づかれることなく、踊りながら門をくぐることができた。
僧侶はちょうど礼拝の最中だった。彼は手に皿を、バラの花をいっぱいに盛った黄金の皿を持っていたが……ミーラが踊りながら神殿に入ってくるのを見ると、手から皿を落としてしまった。彼はひどく腹を立ててミーラに言った。「それはこの神殿のしきたりに反している――女はここには入れないのだ!」
ここでミーラは驚くような答えをしたが、それは神秘家のすべての歴史のなかでもその風変わりなおもむきや、生き生きした活力という点で際立っている。彼女は言った。「なんてことでしょう! 私はクリシュナだけが男性でほかはすべて女だと思っていたのに。今日、私はふたりの男性がいることがわかりました。あなたも男なんですね!」彼女がこのように語りかけるのを聞いて、僧侶は震え出した。たぶん彼女は正しいのだ。
献身者が神を想起するにはふたつの道しかない。スーフィーのように、神を女性として想起するか――神は愛される女性であり神秘家はその恋人だ――あるいはインドの神秘家のように、自分たちを女性として神を男性として想起するか。神は恋人であり彼らは愛される女性だ。
ミーラは言った。「いまここでそれをはっきりさせなさい。自分は男性であると宣言するか、それとも自分もまた女性であると宣言するか」
ミーラに圧倒されたこの気の毒な僧侶は認めざるをえなかった。「私も女性です」
ミーラは言った。「ではたったいまから規則が変わったんです。この神殿には女性しか入ることができません。自分は男だと考える者は入ることができないんです」
これらの神秘家、これらの光明を得た人たちの生涯をよく見たら、あなたはどのような類似性も見つけることはできない。紛れもない独自性しか見つからない。ときに彼らはあまりにも平凡なので彼らを認めることができない。ときに彼らはあまりにも輝かしいので目の見えない人でも彼らの光を見ることができる。だが一般的な規則というものはないし決まった性格というものはない。特定の理想を実現しなければいけないわけではない。
私のアプローチはあなたからすべての理想を取り去ってしまうこと、未来に光明が起こるという考え方そのものを取り去ってしまうことにある。未来は存在しない! じつのところ、光明は未来に起こるという考え方は、現在にいなかったら持ちえない、自己への敬意を避けるためのものでしかない。
教師たちがいた――彼らはマスターではなかった、彼らはあなたと同じように無意識だった。彼らは自分の光明に気づいていなかった。彼らは道徳、修行、手法、いかにして光明を得た人になるかを教えていた。だが彼らの内側の論理が理解できるだろうか。光明を得た人になることができるのなら、また再び光明を得ていない人になってしまう可能性も十分にある。光明を得る手法というものがあるのならあなたに光明を失わせてしまう手法もある。これは単純なことだ。病気になることができるのなら、
健康になることもできるし、また再び病気になることもできる。
光明は獲得しなければならないものではない。獲得したものは奪われてしまうかもしれない。獲得したものは盗まれてしまうかもしれない。獲得したものは無くしてしまうかもしれない。
私はあなたに言おう、あなたは光明そのものだと。
私はあなたに光明を得てほしいのではなく、私はあなたに光明を生きてほしい。まさにこの瞬間から、なにをするときも、光明がそれをせざるをえないようなやり方でそれをやりなさい。
私は西洋の最も重要な人たちのひとり、アラン・ワッツのある言明が好きだ。彼は酔っ払いだったが、禅や光明の最も本質的な部分を西洋に紹介した人だ。彼は学者としてではなく、マスターとして書いた。彼が死ぬ前に、彼がいまだに酒を飲んでいるので、ある弟子が尋ねた。「考えたことがおありですか……ブッダが酒を飲んでいるあなたをごらんになったら、彼はそのことをどう思われるでしょう?」
するとワッツは言った。「問題はないさ。私はいつも光明を得たやり方で酒を飲んでいるんだからね」問題はなにをするかではなく、それをあなたがどのようにやるかが問題だ。そう、私はアラン・ワッツの言明を認める。人は酒を光明を得たやり方で飲むことができるかもしれない。光明にはいかなる限界もあるべきではない。そしてそれはどのような公式も、あなたが従わなければならない特定のパターンも持つべきではない。
光明は個人の体験であるべきだ――誰にとっても他人と比較できない、ユニークな、最も個人的な体験として。これさえ理解できたら、あなたを取り巻く暗いすべての雲が消えていく。
ヴィート・ヴィギャナム、私は何度も何度も繰り返し言うつもりだ。あなたは光明を得ているということが、あなたのなかにしみ込むまでは。そしてあなたはそのためになにひとつ特別なことをする必要がない。たんにありのままの自分として、存在に完全にくつろいで、安らいでいなければならない。どこにも行かず、達成するものはなく、目標もない。すべての目標志向が人びとを惨めにしている。
すべての目標を追いやったら、あなたはまさにこの瞬間に踊り出す――あなたには達成のプロセスに使っていたたくさんのエネルギーがあるからだ。空想のなかではるか遠くに行っていたら、あなたにはここにあるための時間も、空間も、エネルギーもない。自分のすべてのエネルギーをこの瞬間に集めることができたら、そのまさに集まったエネルギーがあなたのハートのなかでダンスになる。そのダンスがあらゆるものを変える、あなたの努力ではなくて。
あるポーランド人が旅行代理店に行ってハワイまでの豪華客船の船旅のチケットを予約した。代理店の職員は彼に奥の部屋に行って書類に記入するように言った。ポーランド人がドアを入ったところで、誰かが頭を叩いて、隅に引っぱっていって金目のものを奪った。
同じ日のもっと後になって、ひとりのイタリア人がハワイ行きの豪華な船旅のチケットを予約するために旅行代理店に入ってきた。奥の部屋に行くように指示され、彼も頭を叩かれて金目のものを盗まれた。
やがてふたりは目を覚まして、自分たちが海の真ん中に浮かぶ小さないかだの上にいることに気がついた。イタリア人はポーランド人の方を見て言った。「帰りは飛行機にしてもらえるかな?」
「どうかなあ」とポーランド人は言った。「去年はしてくれなかったよ」
マーフィー神父はカトリック教会の布教活動をするために選ばれ、北極圏の辺ぴな地方へと派遣された。数か月後、司教が視察に来た。「ここの仕事は気に入りましたか」と司教は尋ねた、「氷やシロクマばかりですが」「とてもすばらしいです」とマーフィー神父は言った。「エスキモーの人たちはとても親切なんです」「気候についてはどうですか?」と司教は尋ねた。「ええ」と神父は言った、「ロザリオとウィスキーがあるかぎり、気候のこともちっとも気になりませんよ」「それを聞いてうれしいです」と司教は言った。「ウィスキーの話が出ましたが、どうですか、一、二杯」「それはいいですね!」とマーフィー神父は言った。「ロザリオ! ウィスキーを持ってきてくれないか?」
ハイミーは少し酔っ払って家に帰ってきた。「ベッキー」と彼は寝室で妻を呼んだ、
「愚痴を言ってくれないか、そうでないとベッドの場所がわからないんだ!」
自分の人生を楽しみなさい。
それはそのままで完璧だ。
完璧主義の考え方は神経症、病理、精神錯乱しかつくりださない。私は平凡であれと教える。私はシンプルであれと教え、自然であれと教え、あなたは到達しようとしてきたところに、まさにわが家にすでにいるということを教える。あちこちを走り回って時間を無駄にしてはいけない。
だがあなたはいつもなにかになれ、何者かになれと言われてきた――あらゆる宗教が私に対立し、あらゆるモラリストが私に反対するのはそのためだ。それは理解できる。なぜなら、もし私が正しかったら、人類をはるか彼方のゴールに向けて駆り立ててきたすべての伝統やすべての教えがきわめて犯罪的であることが証明されるからだ。というのも、彼らは人びとの生きる機会、愛する機会、歌う機会、踊る機会を奪ってきたからだ。そして究極的な意味では、いまここで聖なるものを感じる機会そのものを。ありふれたもののなかに聖なるものを感じることができないかぎり、あなたは知性的な人ではない。自分の小さな行いのなかに感謝、喜び、気づきを表現できないのだとしたら、あなたは惨めなままでいるしかない――この生だけでなくたぶん多くの生に渡って。
あなたに私のような人間を再び見つけられる機会があまり多くあるとは思えない。こういった宗教的な指導者や宣教師たちには多く会うことだろう……ひとりを見つけようとしたら千人ぐらいは見つかるだろう。だが私はあなたの平凡さに最高の敬意を払う。私はありふれたものをこの上もなく崇敬する。私はなにひとつ改良したいとは思わない。何世紀にも渡って人びとは改良に改良を重ねてきたが、なにひとつ改良されてはいない。
私にも機会を与えてほしい。改良をやめなさい。
あなたはそれを知ったら驚くかもしれないが、これまで改良のために使われてきたエネルギーが、あなたのダンスになり、あなたの祝祭になる。
-
(OSHO Times International 日本版103号/発行Osho Japan) 2004 OSHO International Foundation